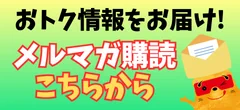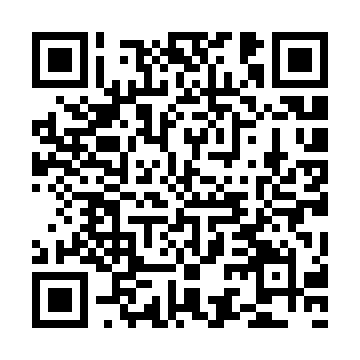ストアブログStore Blog

九州は、一人当たり年間砂糖使用量が全国平均より多いそうです。
どれくらい多いかというと、
なんと10~20%もたくさん砂糖を使うそうです!
だから醤油も甘いわけですね。
では、なぜ「甘く」なったのでしょうか?
主に3つの理由があると言われています。※諸説あります。

①江戸時代の鎖国政策
鎖国時代、唯一の貿易窓口は長崎の出島でした。
出島を通じて輸入された砂糖は、長崎街道を通って本州へ渡りました。
そのため長崎街道は「シュガーロード」とも呼ばれるようにもなりました。
当時の砂糖は高価な貴重品でしたが、沿道の地域では比較的手に入りやすかったので、砂糖を使った料理やお菓子が多く生まれました。
同じように醤油にも砂糖が入るようになったのです。
②温暖な気候
温暖な地域ほど甘いものへの欲求が強くなると言われます。
したがって、南に行くほど塩分控えめで甘い味つけになっていきます。
反対に、東北など寒冷地では塩辛い味が好まれますよね。

③新鮮な魚貝が豊富
九州はどの県も海に面し、すぐ目の前の海で獲れた新鮮な魚貝を食べることが出来ます。
獲れたてのサバ・アジは臭みもなく、旨みと甘みが楽しめます。
佐賀 呼子のイカの生き造りも九州ならではの食べ方ですよね。
その美味しさをそこなわぬよう、醤油はまろやかで甘くなっていったのです。
また一説では、漁師さんたちが船上ですぐ料理が出来るよう、あらかじめ砂糖をとかした醤油を携えて漁に出たそうです。
その土地の気候・風土と味覚は密接に結びついています。
九州の醤油が甘いのは、九州ならではの理由があったようです。
全国各地の「醤油の味」に着目してみると、面白い発見があるかもしれませんね。